伝道<浄土真宗の仏事いちねん>
①「お盆について」(2011/7/6)
お盆―「盂蘭盆会(うらぼんえ)」
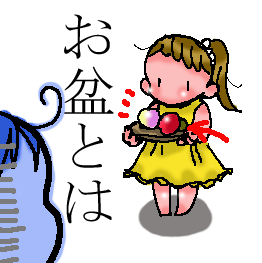 お盆とは正確には
お盆とは正確には
盂蘭盆会(うらぼんえ)といいます。
そのの語源には諸説あります。
たとえば漢語で「倒懸(とうけん)」と訳される「ウランバナ」。
倒懸とは地獄で死者が逆さまに吊るされる苦しみを表していると言われています。
最近有力な説はイラン系の言葉で死者の霊魂を意味する「ウルヴァン」。
ウルヴァンという収穫祭と死者の霊を祀る行事が中国へ伝わって、
仏教と結びつき盂蘭盆会となったという説もあります。
「仏説盂蘭盆経」- 日本へ
仏事としての盂蘭盆会の元は「盂蘭盆経」という中国成立のお経にあります。
お釈迦さまの弟子の目連が、餓鬼道に落ちた亡き母親の苦しみを知り、
師の教えの通り、インドの雨季の間の修行を終えた僧たちに食事を供える
盂蘭盆会を行った所、目連の母は救われて成仏したというお話があります。
このお話が親を大切にする事を尊ぶ中国や日本に受け入れられ広まりました。
こうして中国から日本に始めてこの仏事から伝わったのは飛鳥時代、
推古4年(606年)朝廷の行事として飛鳥寺で行われたのが最初だそうです。
朝廷の恒例行事から各地の大きな寺で行われ、次第に民間に広まっていきました。
ちなみに7月と8月お盆の時期が各地でバラバラなのは、特に農村地帯では農作業の関係でひと月遅れでお盆が行われることが多かったこともあるようです。
日本の「霊」信仰と盂蘭盆会
日本では古来から死者の霊がこの世に戻ってくると信じられてきた時期が
7月半ばの盂蘭盆会時期と重なって、
先祖の霊を家に迎えてお供えや読経など供養をしてあの世へ帰すという
行事として定着したようです。
こうしていま、お盆といえば、
お盆になったら迎え火を炊いて亡き人の霊を迎え、
霊が乗って来るというキュウリの馬やナスの牛を作り、
精霊棚にお供えをしてお坊さんにお経を上げてもらい霊をなぐさめ、
お盆が開けたら送り火を炊いて霊を送り出す…。
(今はここまでやるお家は珍しいかもしれませんが)
浄土真宗のお盆のむかえ方
浄土真宗の寺やご門徒の家でもお盆のお参りは行われます。
しかしその教えからから言えば、上のような事は必要としません。
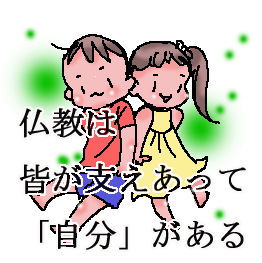 仏教では「無我」という言葉の通り、
仏教では「無我」という言葉の通り、
人が死んだ後も霊魂のようなものが残って何かに生まれ変わったり、
この世やあの世をフラフラするという事はいいません。
私たちはそれぞれの因縁によってたまたまこの「私」という命を生きているだけですが、
どうしてもこの「自分」を確かなものだと思い込むために
さまざまな苦悩が起こるのだと、仏教は教えています。
私達が亡くなった人の「霊」を云々するのも、
「自分」への執着の延長といえるかもしれません。
それもまた私達が大きな迷いの中にいるという事ではないでしょうか。
浄土真宗のお盆はそんな大きな迷いの中に生きる私たちが、
亡くなった方を供養するという話ではありません。
他の法要と同様に、
縁のある亡くなった人を通して私達が仏法を聞き、
その迷っている「自分」を教えてもらう仏事です。
お念仏もお浄土もそのために伝えられてきたのです。
 お盆がきたら
お盆がきたら
お家のお内仏(仏壇)や仏具をキレイにお掃除してください。
(お内仏はお浄土を私たちに表現されたものです。精霊棚の代わりではありません)
迎え火も送り火も野菜の乗り物もいりません。
そしてそのお内仏を前にお参りをしてください。
 お盆のお参りでお坊さんを呼んだ時には一緒にお聖教を読んで
お盆のお参りでお坊さんを呼んだ時には一緒にお聖教を読んで
その意味や仏教の話を聞いてください。
またご縁のあるお寺の盂蘭盆会では法話も行われることでしょう。
その場へ足を運んで皆で一緒にお念仏をして、法話を聞くことも大切です。
お盆とは仏事とはいいながら、
その土地の先祖供養や様々な信仰と混ざり合い
先祖供養からその他無縁の霊も祀って家や共同体の安定を願う行事まで
含みながら今に伝わっています。
発生の元自体そもそも仏事ではなかったのかもしれません。
それでも私たちには、お盆は仏法が説かれそれを聞くことができる
大切な機会の一つです。
お盆を迷いの中にいる事も気づかずにただの年中行事として過ごしていくか、
自分の中の迷いを迷いだと見つめる大事な機縁とするかは、
私たちそれぞれにかかっているのではないでしょうか。
(釈尼慶喜)