伝道<浄土真宗の仏事いちねん>
「お彼岸について」(2011/9/1)
お彼岸は春と秋の1年に二回。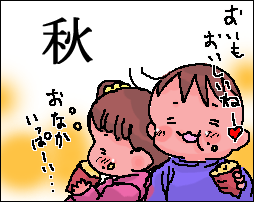
春分の日と秋分の日を期間の真ん中(お中日)として
前後3日間の合わせて一週間の時期に行われる仏事です。
これはインドや中国にはない日本独自のもので、
始まりは聖徳太子の時代の頃、朝廷の宮中行事から
次第に民間へ広まっていったといわれています。
この時期各仏教寺院では彼岸会(ひがんえ)の法要や
各家でのお彼岸のお参りやお墓参りなどが行われてきました。
迷いの「此岸」から「彼岸」へ
「彼岸」という言葉にはいわゆる「あの世」的なイメージなどが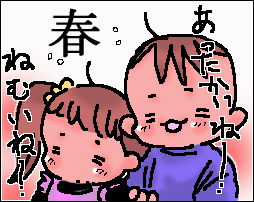 付きまといますが、本来はそういうどこか別世界を指すものではありません。
付きまといますが、本来はそういうどこか別世界を指すものではありません。
迷いと苦しみの中で生き死にする私たちの在り方を此岸(しがん)と表して
そこから解放された仏教の理想の境地を「彼岸」と表現したものです。
彼岸会は季節的に過ごしやすいこの時期、仏道修行に励んで
その理想の境地を目指して行われてきた仏事でした。
また浄土教とのつながりでいえば、
お中日の春分・秋分の日は太陽が真東から登り真西へ沈むことから
日が沈む西方にあると言われていた極楽浄土を雑念を払ってイメージする
「日想観」という修行に最適であるという中国は善導大士の教えにより
浄土教徒が浄土を慕って西方を拝むということが流行したともいわれています。
浄土真宗のお盆
私たちの浄土真宗では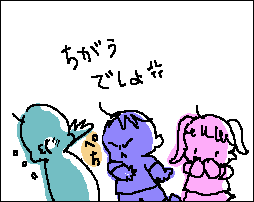 本願寺の第三代覚如聖人の著作「改邪抄」などにも
本願寺の第三代覚如聖人の著作「改邪抄」などにも
彼岸会についての文があり、
本山を始め各寺院でも彼岸会は行われてきましたが、
春と秋の彼岸に特別に念仏修行に励むという意味ではなく、
彼岸会を縁に仏徳を讃え、普段からの聞法(教えを聞くこと)と
信心の確認の場の一つとして行われてきたものと思われます。
現在の浄土真宗のお寺でも彼岸会は行われます。
仏道修行と力んで特別な事をすることも無いし
日想観と西を向いて浄土を拝んだりもしません。
お彼岸にはお家ではお内仏(お仏壇)をきれいに掃除して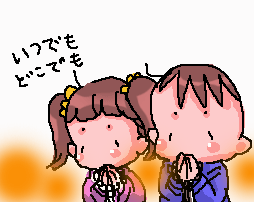 打敷(うちしき)やお花やお供えなどをして
打敷(うちしき)やお花やお供えなどをして
いつもの通りのお参りをします。
お墓参りでも通常通り特別なことはしません。
ただそれは亡き人の供養のためではなく、亡き人がご縁となってお墓やお内仏やお寺へお参りして「私に」念仏を唱えさせてくれて、法話を聞かせてくれる。
そうして亡き人の促しによって「私が」仏法に出遇わせていただく
そんな大切な機会の一つとして、大切に迎えていただければと思います。
(釈尼慶喜)